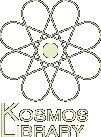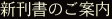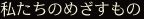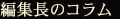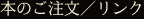第4回
先月、シンポジウム「援助交際=少女売春をどうするか 問われる学校・家庭・社会の教育力」に参加させていただき、いろいろ参考になるお話をたくさん聞く機会に恵まれました。今回はそのことにからんで、少々感想めいたものを書かせていただければと思います。
全体を通じて特に印象に残ったことのひとつは、「オヤジ」の評判がはなはだしく悪いということです。先日、作家の柳美里さんがあるインタビューで、日本の男たちは、バブル経済があれほど精神的荒廃をもたらしたにもかかわらず、心の奥ではまたあのような経済的浮かれ騒ぎを味わえることを願っているようだと指摘していました。みずからの価値観・生き方を根源的に変え、より高い生へと発達するためのまさに千載一遇のチャンスが来ているかもしれないというのに、それから目をそむけ、「発達拒否」状態に陥っているかのようです。
『新潮 』3月号に載った「地獄に堕ちた『戦後』教育」の著者堺市立若松台小学校教諭樽谷賢二氏は、今問題になっている「学級崩壊」の原因について、次のように指摘しています。「私の経験では、〈学級崩壊〉の裏には必ずといっていいほど〈家庭崩壊〉があるようだ。とはいえ、片親の家庭であっても、母親や父親が自分の子供をしっかり見すえて立派な子育てをしている例も数多く知っている。そういう親には、私は一教師として頭の下がる思いがする。だから〈家庭崩壊〉が必ずしも子供の荒れに結びつくとはいえない。しかし、小学校段階では逆は真なりといえそうだ。つまり荒れている子供達は、かなりの確率で自分の欲望追求に忙しく、子供にまともに向きあわず〈子捨て〉をしてしまった親の元にいる。もう一つのタイプは、超過保護で、とにかく子供のいうことは何でも聞き入れるという、お子様が御主人様の家庭に育った子供である。この両タイプがドッキングすると収拾がつかなくなる」。
で、樽谷先生はこのドッキングの具体的な例を挙げて説明しているのですが、なかでも暴れん坊のリーダー格の〈親分〉の異名をとる生徒についての箇所には思わず唖然としてしまいました。出張で留守だった校長室内で箒でチャンバラごっこしているのを見て、「蛍光灯にでもあたったら大怪我だぞ、やめないか」と先生が注意すると、予想に反して暴れん坊たちはすなおにやめました。そこで、「えらい、よく言うこと聞くやないか」と言うと、〈親分〉は「センセ、どつくやろ」と返答しました。で、先生は「そら、こんな狭い部屋で箒ふりまわしてたら危ないがな。やめないと一発どついてたやろな。ところで君はどんな時大人の言うことを聞くんや」とついでに聞いてみると、〈親分〉は間髪を置かずに「力と金や」と言ったそうです。
しかも、このように暴れまわっていた子供達の親はおおむね学校批判派だったそうです。さらに、「ここ十年ほどの間に子供達は明らかに変質してしまった。社会全体からみればいわゆるバブルがはじけた頃から子供達の変質は始まったように見える。それまでの日本社会は大きく経済成長を遂げる道をひた走っていた。大人達は馬車馬のように働いた。社会そのものが一つの目標に向かって動いていた。そういう時代には、子供達は大きく崩れない。大人社会が目標を見失い退廃しだすと、子供達も変質する。子供というのはいつの時代でも大人の鏡である。昨今のように大人社会のどこを見ても不透明な時代に、子供にしゃんとしろと言ってもどだい無理なことである」。〈親分〉と呼ばれている子供の父親がどんな人間かはわかりませんが、援助交際している女子高生に大金をあげている成り金の「オヤジ」の姿を思い浮かべてしまうのは筆者だけでしょうか?
◇
つい先日、サングラハに連載を寄稿中の田辺先生から『グノーシスの神話』(大貫隆訳・著 岩波書店)という面白そうな本が刊行されたというお知らせをいただき、筆者も早速書店で買い求めました。グノーシス主義についてはここで簡単に紹介することはとても無理ですので、興味のある方は同書を入手されることをお薦めしておきます。一口で言えば、「クノーシス主義は古代末期から近代に至るまで、地中海およびヨーロッパ文化の実にさまざまな領域、すなわちユダヤ教、キリスト教、イスラム教という歴史的世界宗教、神学、哲学、神秘主義思想、科学史などの領域において、表の文化に対する裏の文化として見え隠れしながら、連綿とその影響を及ぼし続けてきた」ものであり、その最大の特徴は「世界を巨大な悪と見て、それを拒否あるいは逃避して生きようとする」ということです。そしてこの姿勢からは「現実世界を人間世界にとって益となる方向へ変革すること」は無意味であるがゆえに、あり得ない選択肢となるということです。
ここからして大変興味深いのは、「グノーシス症候群」と呼ぶべきものがあるということです。で、同書の「結び グノーシス主義と現代」の中の「終りなき日常とグノーシス主義」という一節で、大貫先生は次のように述べています。
世界拒否あるいは逃避という「グノーシス症候群」は、現代日本の社会状況の中では、むしろ「テレクラ売春」、「ブルセラ」、「援助交際」、「オヤジ狩り」をキータームとする女子高生の生態の中に垣間見られる。宮台真司はこの生態を指して、それは「終りなき日常」を生きるための女子高生たちの知恵だと言う。「『終りなき日常』という言葉で私が言いたかったことは、こんなことだ。子供が原っぱで遊び、家電製品もロクに揃っていないような近代過渡期の社会では、『頑張れば自分も家族も社会ももっと豊かになる』という具合に、人々が社会の未来に『輝く希望』を託すのが当たり前。でも社会が成熟してくると、人間も社会もこれから大して変りはしないというイメージになっていく。自分を取り巻くサエない日常が、ひっくり返るなんてことはこれからもありえない。そのことを自分に納得させながら、人々は生きるようになる。そんな『終りなき日常』を自分や他人を傷つけないで生きるには、知恵が必要になる」宮台真司『世紀末の作法)。
大貫先生はさらに、『世紀末精神世界』(WAVE出版)の著者、ユング心理学者入江良平氏の言葉を借りて、そこに見えてくるのは「極度に陰鬱な世界像」であり、「この『輝きを失った混濁した世界』には宇宙的な調和も、未来の希望も、魂の内なる輝きもありません。一切は意味を剥奪され、すべてが淀む灰色の世界。それが『終りなき日常』の原風景なのです」という宮台さんの説明を引用し、さらに次のように述べています。
宮台によれば、性を売りながら女子高生たちはこのような世界を拒んでいるのだと言う。それでは、性を買う「オヤジ」たちはどうなのか。たとえどれほど女子高生たちの目に世界を受容した大人の代表と見えようと、実はそうではないのではないか。増えつづける一方の中高年の自殺は、彼らも世界から逃げようとしていることの証しであろう。この世界拒否と世界逃避にグノーシス主義症候群が顕在化していると述べることは、決して過言ではないであろう。……しかし、「終りなき日常」の原風景はグノーシス主義の半分に過ぎない。グノーシス主義者は、……現実の世界に対する絶対的な違和感の中でこそ、本来の自己がそれを無限に超越する価値であると信じるからである。
グノーシスの『魂の解明』という文書には、地上に落下して汚辱にまみれながらも、自分の神的本質に目覚めて、光の世界の父のもとへ戻ってゆく魂(女性)の姿が描かれているそうです。これに対して大貫先生は、「オヤジをカモり、徹底して戦略的に振る舞う現実の女子高生たちにとって、オヤジという存在は『汚れ』かつ『世界を受容した者』の象徴だ。そのオヤジ相手に売春しまくる彼女たちは『汚れ』てはいても、『世界を受容していない』。その意味でイノセントな存在だ」という宮台さんの言葉を引用しつつも、自分は無垢で、すべて世界が悪いのだというのは、高校生の実存理解としては仕方がないかもしれないが、この「新しいイノセンス」は余りに楽天主義だと評しています。(なお、宮台真司氏の言説とそれに対する批判に関しては、諸富祥彦編著/トランスパーソナルな仲間たち著
『〈宮台真司〉をぶっとばせ!--“終わらない日常”批判』(コスモス・ライブラリー 1999年)参照)
◇
今回のシンポジウムでは「性」というものがかなり正面きって論じられ、いろいろ勉強になりました。で、宮台さんが言うような「魂に良いセックス」というものが本当にあるのだろうか、そもそもその場合の「魂」という言葉にはどのような意味がこめられているのだろう、とずっと疑問でいたのですが、最近、これについて多くのヒントを与えてくれるような本が出版されました。それはアメリカ、アラバマ州で開業するユング派分析家、ナンシー・クオールズ‐コルベット著『聖娼』(日本評論社)という本です。
「聖娼」というのはキリスト教以前の母権的宗教の大母神の神殿において、女神の化身である人間の女性が、肉体と魂の交歓を呼び起こすために、その神殿に詣でる異邦人の男性と交わる役を果たす巫女のことです。セクシュアリティ(性)とスピリチュアリティ(霊性)とを極端に分離してしまった現代人の論理的な知性にとってはパラドックスと映るこの聖娼を調べていくと、そこに霊性とセックスとをひとつに融合させる元型的な女性のイメージが浮かび上がってきます。これに対して、「今わが国で騒がれている『援助交際』などは、『聖娼』にまつわることが極端に歪んだ形をとって出現してきていることに気づくであろう」と「刊行に寄せて」の中で河合隼夫先生は指摘しています。
著者のコルベットは聖娼のイメージを明らかにするため、ある文献から次の箇所を引用しています。
美と善意と比類なき結びつき(カリスcharis、ラテン語のcharitas)にかかわっているため、しばしばカリスたち、あるいは美の女神たちとして知られていた。カリス(charis)はのちに「慈善(charity)と訳されるようになる。実際にカリスは、母の愛、優しさ、慰め、神秘的啓示、そして性交がすべて一体となったヒンズー教の慈悲(karuna)と同様のものであった。
実際、インドには「デヴァダーシー」と呼ばれる寺院専属の聖娼(hierodule)がたくさんいたのです。