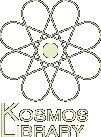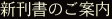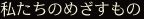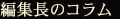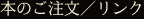さらにルイスは「パーティーでしらふな人が二人いたら、もっと愉快になれる。三人になったらもっといい。あなたから始めなさい。そうすれば他の人々も変り始め、ついにはすっかり夢から覚め、パーティーにいる全員がしらふになるだろう」と言っています。
これを読んだ後、ルイスが言う意味で“しらふ”な人についていろいろ思い浮かべているうちにふと思い出したのが、あの世界的に有名な小説家フランツ・カフカでした。ただし『カフカとの対話』(筑摩叢書)の中で描かれているものしてのカフカですが。ずっと以前ざっと読んだとき、小説家というよりは若い賢者あるいは覚者のような印象を受けたのを憶えています。で、この度改めて目を通してみたところ、その印象は間違いではなかったことを確認できました。そこで今回は、“しらふな人”としてのカフカの印象をお伝えするため、同書から語録風にカフカの言葉を引用してみたいと思います。
著者はグスタフ・ヤノーホと言い、彼の父は、カフカ(1883-1924)が当時勤務していた「労働者障害保険局」の同僚でした。そこで父の紹介で、当時17歳の著者はカフカと知己になり、彼と対話する機会に恵まれ、それらを回想記としてまとめたのです。二人が出会ったのは1920年、カフカが36歳の時でした。ヤノーホは「日本語版に寄せて」の中で次のようにカフカの印象を描いています。「フランツ・カフカの外貌--彼の丈高い、しかも謙虚な姿、清らかな、魂の奥底からわき出る善意の微笑、彼が人生に対して、自身の病気に対して、とりわけこの私の向こう見ずな青春に対して示した忍耐、彼の大きい、真珠母のような灰色の眼と、頑丈な、しかも身振りをする際には途方もなくしなやかで抑制された両の手--それらは、明澄な、この世のものならぬ存在の現前(げんぜん)のように、容易ならぬ生涯を通じての私の伴侶となったのです。フランツ・カフカのもつ人間らしさと崇高さが、彼に、地上のものならぬ存在という直截(ちょくせつ)な印象を与えたといっていいでしょう」
◇
人は、どうあっても書かねばならぬものだけを、書かねばなりません。
◇
(デヴィッド・ガーネット作『狐になった貴婦人』という本に関連して)
人間は誰もが、自分の持ち歩いている鉄格子の中に暮らしています。だから今日では、動物のことをこれほど多く書くのです。これは自由で自然な生活への憧憬の現れです。しかし、人間にとって自然な生活とは人間の生活でなければならない。しかもそれが分からない。分かろうとしないのです。人間の生存があまりにも困難になったために、人はそれをせめて幻想のなかで、振るい落とそうとするのです。
(「それはフランス革命の前によく似た運動です。当時は、自然に還れと言っていました」というヤノーホのコメントに対して)
そう。しかし今日ではもっと進んでいます。人はそう言うばかりではない--実行しているのです。人間が動物に戻ってゆきます。その方が人間の生活よりもずっと簡単なのだ。居心地よく家畜の群に投じて、人は都市の街路を仕事場に向って行進します。飼葉桶と満足感に向って。それはちょうど役所におけるように、一分の狂いもなく計測された生活です。奇蹟というものはなく、正確な使用説明書と、書式と、訓令の世界です。人間は自由と責任を怖れ、その故にむしろ、自分ででっち上げた鉄格子の中に窒息することを、よしとするのです。
◇
(ユダヤ人の両親が「カフカ商会」を経営し、立派な邸を所有する金持であることをヤノーホに指摘されて)
富とはなんでしょう。誰にだって、古ぼけたシャツ一枚がすでに富です。ある者は億万の財を抱いて貧しいのです。富とは全く相対的で、飽き足りることのないものだ。究極のところ、在る一つの特殊な状況にすぎないのです。富とは、人が所有する物件への従属を意味します。そうしたものを人は所有しているが、さらに新たな所有によって、つまり、つねに新たな従属によって消滅を防がねばならぬ。それはつまり物質と化した不安定、にすぎないのです。ともかく--それは両親のものなので、私のではありません。
◇
(本好きのヤノーホが「僕は書物がなくては生きてゆけないような気がします。僕にとって、本は世界です」と言ったのに対して)
それは間違っています。本は世界の代用となるものではない。この人生においては、一切がその意味と使命を帯びていて、それを何か他のもので余すところなく満たすことは出来ない。人間は--たとえば--その体験を、誰か代理人の手で我がものとすることはできないのです。世界と書物についても同様です。人は書物のなかに人生を、まるで小鳥を籠に捕えるように、閉じ込めようとする。が、そうはいかない。逆に、人間は書物の抽象作用のなかから、自己自身を閉じ込める〈体系の檻〉を作り上げるにすぎません。哲学者とは、さまざまな鳥籠を背負った、美々しい羽根衣装のパパゲーノ(モツアルトの歌劇「魔笛」中の滑稽な人物。鳥を捕えて大きな鳥籠に入れて売り歩いている。全身多彩な羽根に覆われている)にすぎないのです。
◇
人生から、人は比較的容易に多くの書物を抽き出すことが出来ます。しかし書物からとり出せる人生は、じつに、いや完全に微々たるものです。
◇
(ヤノーホが多数の新刊書を見せてうっとりしているのに対して)
書物は一種の麻酔剤です……あなたは蜉蝣(かげろう)のようなものにあまりにかかずらいすぎているようです。こうした現代の書物の大部分は、〈今日〉のゆらめく反映にすぎない。それは瞬く間に消えてしまうものです。あなたはもっと古いものをお読みにならなければ。古典作家たちを。ゲーテを。古いものには、その奥底の価値が滲み出ています……それは持続性ということです。ただ新しいというだけのものは、無常そのものです。今日の美しさは、明日は滑稽に見えようがためだ。これが世の文芸(リテラトウル)の歩む道です。
◇
(エドガー・アラン・ポーが「評判の酒飲みだったそうですね」というヤノーホのコメントに対して)
ポーは病気でした。惨めな人間で、世間に対して無防備でした。だから彼は酩酊のなかに逃れたのです。空想力は彼にとっては、その身を支える橦木杖(しゅもくづえ)でしかなかった。彼はこの世に定着するために、この世をはなれた無気味な物語を書いたのです。これは至極当然のことだ。空想のなかには、現実におけるほど多くの落とし陥はないのです。
◇
(スティーヴンスンの『宝島』に関連して)
現実こそ、世界と人間を造型する、最も強力な力です。現実は、〈現〉にその〈実〉を挙げる。だからこそそれは〈現実〉なのです。人はそれから逃れることはできない。夢とは廻り道にすぎず、結局は一番手近な経験の世界に舞い戻るのが落ちなのです。スティーブンスンは南海の島へ。
◇
人間の大多数には、およそ生活というものがないのだから、彼らは、丁度小さな珊瑚虫が岩礁にこびりつくように、人生にしがみついているにすぎません。しかも人間は、この原始的な生物よりもはるかに貧しいのです。人間には波浪に逆らう固い岩礁がない。また自分を守る石灰質の殻もない。彼は腐食性の胆汁粘液を吐き出して、それが彼を他の人間から遠ざけるために、いよいよ弱く孤独になるのです。
◇
(フランスの作家アンリ・バルビュスの『十字砲火』と『クラルテ』に関連して)
砲火、というのは戦争の光景であって、真相にマッチしています。明晰(クラルテ)とは、しかし夢と願望による表題です。戦争のために、われわれは歪んだ鏡で出来た迷路のなかに放り込まれたのです。われわれは見せかけの遠近感(パースペクティブ)に引きずりまわされて、よろめいています。〈えせ〉予言者や山師どもに惑わされ、その犠牲となって、眼や耳を安直な幸福用速効薬で塗りつぶされ、鏡の落とし穴から一つの土牢へ、また一つの土牢へと墜落してゆくのです。
(「何が僕たちをこんな状況に陥れ入れたのですか」というヤノーホの問いかけに対して)
私たちの、人間の分を超えた貪欲と虚栄、私たちの不遜な権力意志のなせる業です。私たちは本当の価値ではないところの価値をもとめてあがいています。そして私たち人間の全存在が結びついているさまざまなものを、無思慮にも破壊するのです。これは錯乱であり、そのために私たちは泥にまみれているのです。
◇
(オスワルト・シュペングラーはその『西欧の没落』の理論を、そっくりゲーテの『ファウスト』から掬み取ったのだと、友人のアルフレート・ケンプが言っていました」という、ヤノーホの指摘に対して)
大いにありそうなことです。多くのいわゆる学者たちは、詩人の世界を別な学問の平面に移調し、それでもって名声と意義を得るのです。
◇
(「御意見によりますと、新聞は真実に奉仕していないことになります」というヤノーホの問いかけに対して)
真実は、人生において真に偉大で価値高い数少ないものの一つです。これは購うことのできぬものです。愛や美と同様、それは人間に贈られるものです。新聞は、しかし売買される商品です。
◇
プロシャ式の歩調と、大勢のダンサーを集めたダンスには同じ目的があるのです。どちらも個性を抑圧するのです。兵隊もダンスガールも、もはや自由な個人ではなく、拘束された集団の一部であり、およそ彼らの本質のそぐわぬ命令に従って動くのです。だから彼らは、すべての命令者の理想とするところです。何事も説明したり、変革する必要はない。命令で充分だ。兵隊もダンスガールも、人形のように行進します。そのことが、それ自身まるでつまらぬ命令者を偉大に見せるのです。
◇
(ムッソリーニの肖像を指さして)
この男は、猛獣使いのようなグロテスクな口と、いかさま役者が真摯な深さを装ったようなどんぐり眼をしています。要するに彼は、集団として働きのない、非政治的にして政治的なダンスガールを操る、演芸場の元締といったところです。
◇
(1922年に英国がインド国民会議派の最有力者マハトマ・ガンジーを捕えたとき)
これでガンジーの運動が勝つことは明らかになりました。ガンジーの投獄は彼の党派に、いよいよ大きな躍進を可能にするでしょう。殉教者のいない運動はすべて、成功ばかりを狙う投機師どもの利益共同体に堕してしまうからです。滔々たる流れが、未来の希望の一切を腐らせる水溜りと化するのです。何故なら思想(イデー)というものは--およそこの世で超個人的な価値をもつすべてのものと同じく--個人的な犠牲によってのみ生きるからです。
◇
(ある書店のショーウインドーに、神智論者(セオゾーフ)ルドルフ・シュタイナーの講演の案内が出ているのを見てヤノーホが、「父の意見では、彼は一種の神秘家(ミスタゴーゲ)で、金持のために口当りのいい宗教の代用品を製造しているとのことです」と言い、さらに「彼は予言者なのか、それとも山師なのですか」と尋ねたのに対して)
私にはわからない。彼のことは、私にはなかなか合点がゆきません。彼はおそろしく言葉に巧みな男です。この特性はしかしまた、山師の武器ともなるのです。シュタイナーが山師だと言う積りはない。しかしそれもあり得ることかも知れないのです。詐欺師はつねに、困難な問題を安易なやり方で解こうとします。ところでシュタイナーの取組む問題は、およそ困難極まりないものでしょう。それは、意識と存在との間の暗い傷口、限りある水滴と無限の大海との間の緊張ということです。ここではゲーテの姿勢(「ものを考える人間の至上の幸福は、究め得るものを究めつくし、究め難いものを静かに尊敬することである」と『箴言と省察』の中で述べた)だけが正しいのだと、私は思います。人は、認識し得ぬものを静かに畏敬しつつ、すべての認識し得るものを整理し、摂取しなければなりません。
◇
資本主義とは、内から外へ、外から内へ、上から下へ、下から上へと連なる隷属性の組織です。一切が隷属し、一切が鎖につながれている。資本主義は世界及び人間の魂の一つの状況です。