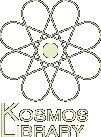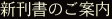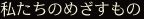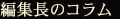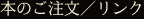第22回 二種類のナショナリズムと人間の解放--竹内好著『アジアと日本』その他から
意見は人と人とを分かつが、事実は人と人とを結びつける。
--クリシュナムルティ
私の意見では、人口の24%が深い変容的、超個的な霊性に取り組んでいることはない。『アクエリアン革命』や『統合的文化』によって主張された数字とは程遠く、およそ1%ぐらいだろう--それでもなお数百万人!
☆
熱狂的応援で何かと話題の日本人サポーターについて「若者がともに国歌を歌って応援するのは素晴らしい、今までわが国ではそういうことをすると、変に国家主義だと批判する風潮があったが、世界の国々でのサポーターが自国を懸命に応援する姿勢を見て、当然のことだとやっと気付いたのではないか。愛国心、応援もやっと国際レベルになった」と評価した。
☆
一九五五年の春、アジア・アフリカ会議の開催にあたって、インドのネルー首相が「この会議で何が論議されるかということより、こういう会議が開催されること自体が重大だ」と述べた。この一言は、アジアが世界で発言力をもつようになった今日の新しい動きを、端的に言いあらわしている。
日本の場合は、みずからのドレイ根性をなくさぬまま、主人に成り上がろうとし、その過程で同じドレイとして本来連帯すべきだったアジア諸国民、とりわけ中国・韓国人に手酷い仕打ちを加えたわけです。ドレイは他の国のドレイに対して最も残忍になりうるのです。E・H・ノーマン著『日本における兵士と農民』には、次のように書いてあるそうです。「みずからは徴兵軍隊に召集されて不自由な主体である一般日本人は、みずから意識せずして他国民に奴隷の足枷を打付ける代行人となった。他人を奴隷化するために純粋に自由な人間を使用することは不可能である。反対に、最も残忍で無恥な奴隷は、他人の自由の最も無慈悲且つ有力な剥奪者となる。」ですから、支配被支配の関係そのものの排除へと向かおうとする意識変革が不可欠なのです。
「労農運動も水平運動の一翼であると思って進んだ」と語る治一郎の胸には、水平運動とはなにも非被差別部落民の解放だけを目指そうという独善的で偏狭な運動ではなく、部落外にある人びとも階級的苦しみにあえいでいるのなら、ともに手をたずさえて人間解放を克ちとり、「人類最高の完成」を目指そうという遠大な思想であったはずだとの思いが横たわっていたことだろう。まして差別される側だけでなく、資本家や貴族、軍人をふくめた差別する側の解放も期さなければ、「人類最高の完成」など望めはしない。治一郎の水平主義とは、むしろ北原が指摘したような排他主義からはるかに遠くかけ離れた、人類共同の楽園を求めるこころのことではなかったかと私は思う。
綱領
一、我々特殊部落民は部落民自身の行動によって絶対の解放を期す
一、我々特殊部落民は絶対に経済と自由と職業の自由を社会に要求し、以て獲得を期す
一、我々は人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成に向かって突進す
一、我々特殊部落民は部落民自身の行動によって絶対の解放を期す
一、我々特殊部落民は絶対に経済と自由と職業の自由を社会に要求し、以て獲得を期す
一、我々は人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成に向かって突進す
兄弟よ。