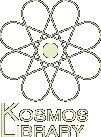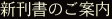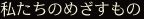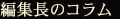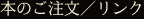第26回 図書館のネズミ
ところで皆さんは「図書館のネズミ」というのをご存知でしょうか?
インターネットで調べたところ、図書館のネズミとは、イタリア語で「本の虫」(topo di biblioteca) のことを言うそうです。編者がこの言葉を知ったのは、クリシュナムルティ財団関係者の一人、ルーベン・エルネスト・フェルドマン‐ ゴンザレスが記憶を頼りにまとめた、クリシュナムルティとの対話録の中ででした。この対話録はとてもおもしろいので、『片隅からの自由― ― クリシュナムルティに学ぶ』中に「クリシュナムルティとの対話録」として収録しておきました。以下はその一節( 一九七八年六月、ブロックウッド・パーク) です。
私は十日間続けてクリシュナムルティと食事を共にした。私は、彼、ボーム博士と彼の妻、ジンバリスト夫人、シモンズ夫人、そして当時インドのリシ・バレー・スクールの校長だったナラヤン氏と同席した。六月二二日と二三日には、クリシュナムルティ、ボーム、ナラヤン、そしてスリランカから来た仏教徒ラフラ博士との討論をフィルムに撮るため、三台のカメラが設置された。クリシュナムルティは参加するよう私を招いたが、いつものように私は辞退した。
翌日の昼食の時、私は仏教の専門家についてどう思うか尋ねた。クリシュナムルティは言った。「ご存じのように、読んだことを“反唱する”ことしかできない物知り[図書館のネズミ――いろいろな本を読みかじって、その内容を訳知り顔で話す人]がたくさんいます。彼らは、読んだことを“生きる”ことができないのです。討論の間中、洞察はただの一瞬もありませんでした。彼は、(クリシュナムルティが言う)新しいものと古いもの(仏 教)を比較する以外に何もしなかったのです。彼はあらゆるものを仏陀に引き比べているだけで、仏陀になろうとは思わないのです。
翌日の昼食の時、私は仏教の専門家についてどう思うか尋ねた。クリシュナムルティは言った。「ご存じのように、読んだことを“反唱する”ことしかできない物知り[図書館のネズミ――いろいろな本を読みかじって、その内容を訳知り顔で話す人]がたくさんいます。彼らは、読んだことを“生きる”ことができないのです。討論の間中、洞察はただの一瞬もありませんでした。彼は、(クリシュナムルティが言う)新しいものと古いもの(仏 教)を比較する以外に何もしなかったのです。彼はあらゆるものを仏陀に引き比べているだけで、仏陀になろうとは思わないのです。
最近(5月の連休ごろから) 、健康のためもあって日曜日に散歩をするようにしているのですが、その途中で古書店にちょっと立ち寄ったりしています。そのうちの一つの店で二冊ほど買ったところ薄い紙袋に入れてくれたので、それを何気なく見たら、次のような「ネズミ」の絵がありました! そうか、これが例の「図書館のネズミ」なのか!
そう思って思わず微笑んでしまいました。その表情はネズミというよりは黒ネコに近いような感じで、とてもユーモラスです。以来、このネズミの絵がすっかり気に入ってしまいました。

なお、その時買った二冊というのは『維新の精神』( 藤田省三、みすず書房、一九六七年) と『英雄と聖人』( 古川哲史、福村書店、一九五八年) です。どちらも値段が105円で、申し訳ないほど格安でした!
もっとも『維新の精神』は鉛筆でたくさん書き込みがありましたが、読むには支障がありません。どちらも全部きちんと読んだわけではなく、まさに「読みかじった」程度ですが、予想外に面白い本で、得るところ大でした。
『維新の精神』
まず『維新の精神』ですが、著者の藤田省三(1927〜2003)は、ウィキペディアで次のように紹介されています。
思想史家・政治学者(日本思想史)。戦後を代表するリベラル派知識人。丸山眞男の弟子で、寡作ではあるが丸山学派を代表する。天皇制国家の構造分析は戦後思想史において画期的意味をもちつづける。鶴見俊輔らとともに行った『共同研究 転向』では中心的役割を果す。みすず書房から『藤田省三著作集』が刊行されている。
愛媛県出身。敗戦で陸軍予備士官学校から大三島に帰郷していた18歳の時、今治市の書店で丸山の「超国家主義の論理と心理」を読んだことが、役人養成の東大法学部ではなく、「丸山ゼミ」に入学するきっかけとなる。
直腸癌と肺炎で死去、「西多摩再生の森」で自然葬された。葬送の自由をすすめる会会員。
愛媛県出身。敗戦で陸軍予備士官学校から大三島に帰郷していた18歳の時、今治市の書店で丸山の「超国家主義の論理と心理」を読んだことが、役人養成の東大法学部ではなく、「丸山ゼミ」に入学するきっかけとなる。
直腸癌と肺炎で死去、「西多摩再生の森」で自然葬された。葬送の自由をすすめる会会員。
ちなみに、藤田さんの出身地愛媛県関係者には編者の知人が数人います。『新しい精神世界を求めて― ― ドペシュワルカールの「クリシュナムルティ論」を読む』の著者、稲瀬吉雄さん、そして塾を経営しながら柑橘類栽培や地元の様々な活動に従事していらっしゃる国貞直秀さんです。また、『自己牢獄を超えて― ― 仏教心理学入門』の著者、藤田一照さんも愛媛県出身です(現在は、神奈川県在住)。また、浅草にある編者の菩提寺・日輪寺は時宗の寺で、ご存知のように時宗の開祖一遍さんは伊予( 愛媛) の出身です。ということで、ちょっとしたご縁を感じます。
藤田さんは知識人といっても、軟弱ではなく、とても勇敢な人で、『維新の精神』に収録された「当事者優位の原理― ― テロリズムと支配者への抗議」中では、危険を顧みずに右翼に対して手厳しい批判をおこなっています。これは「嶋中事件」という、1961年に起こった右翼テロ事件に対するものです。ウィキペディアによれば、これは次のような事件でした。
雑誌『中央公論』1960年12月号に掲載された深沢七郎の小説『風流夢譚』(ふうりゅうゆめものがたり)の中で、皇太子妃が民衆に殺される部分や民衆が皇居を襲撃した部分が描かれたことなどについて、不敬であるとして右翼が抗議し、1961年2月1日に大日本愛国党の党員だった17歳の少年が、中央公論社社長の嶋中鵬二宅に押しかけた。少年は嶋中との面会を求めたが嶋中は不在で、雅子夫人が重傷を負い50歳の家政婦が刺殺された。少年は事件の翌日に警察に自首して逮捕された。
岸首相襲撃事件、浅沼稲次郎暗殺事件など、安保闘争に対抗するかのような一連の事件の1つであった。
この事件の経緯や顛末について関心のある方はウィキペディアをご覧になってください。藤田さんが問題にしているのは、「右翼の余計なおせっかい」、つまり「不法な無権代理行為」で、具体的には次のようなことです。
岸首相襲撃事件、浅沼稲次郎暗殺事件など、安保闘争に対抗するかのような一連の事件の1つであった。
深沢事件についても陳謝を要求する資格は、――その要求が妥当なものであるかどうかは全く別として(現に私は深沢氏の作品を非常に秀れた日本文化論として受け入れるべきものだと評価している)――皇太子とその夫人にのみあるのであって、右翼などにはありはしない。いわんや「世間」に向って陳謝することを雑誌に向って強要したりするのは、全くの方角違いを敢てしているのである。つまり右翼テロリストは、そうしてくれと依頼してもいない皇太子に勝手になり代り、僭越にも「日本国民」に勝手になり代り、更に政府にすらなり代って、陳謝を他人に強要したり報復の代行を行ったりしているのである。「日本国民」も日本政府も皇太子も自分が知らぬ間になり代られて、凶暴沙汰を惹き起されているというのに、これを黙許しておいてよいのであろうか。
右翼のこうした勝手な行動がなぜまかり通っているのか?
その背景を藤田さんは日本の明治以来の政治・社会の変遷を辿りながらえぐり出しています。こうしたテロ行為は依然としてこの国の政治風土に深く根ざしており、今もなお地底から噴出してきます。
『維新の精神』には他にも幕末から維新への移行当時の状況や、「大正デモクラシー精神」の代表例としての内村鑑三のことなど、いろいろ参考になることが書かれています。特に、内村の「再臨運動」に言及している箇所があり、これは、新刊『回想のクリシュナムルティ・第1 部: 最初の一歩……』の「いまなぜクリシュナムルティなのか?――訳者あとがきに代えて」の中で引用させてもらいましたので、興味のある方はご覧になってください。
最後に一つだけ、参考までにご紹介したい言葉があります。それは「横行」です。辞書には次のように出ています。「1 .自由気ままに歩きまわること。「やくざが街を― ― する」2.悪事がしきりに行われること。ほしいままに振る舞うこと。「汚職が― ― する」3.横へ進むこと。横向きに歩くこと。「カニの― ― 」」
ご存知のように、維新前夜にはいわゆる「浪人」がたくさん「横行」していました。竜馬もそうですが、自分の藩から脱出( 脱藩) して、志を同じくする他の浪人たちと連携して、新しい国家創建をめざしたわけです。江戸幕府側から見れば、彼らは上からの意見に従わない、まさに不穏分子で、全国を横へ横へと歩きまわり、「勝手な」議論を提( ひっさ) げて、論争に連絡にと飛び廻ったのです。こうした浪人たちは、「身分」によることなく、「志」のみによって相互に判断し結集する「志士」になり、やがて幕府に代って「天下国家」を担うようになったというわけです。こうした志士たちの活動は、現在様々な形で見られる「ネットワーク」的活動の「走り」だったと言えるかもしれません。「横行」には否定的な意味合いが強いですが、それはあくまでも支配者側から見た場合であって、少なくとも維新前夜においてはむしろ積極的な意味合いを持っていたのです。また、「封建の範囲を超越して」自らの選択によって行動していたという意味で、「自己選択」の先駆者でもあったと言えるのではないでしょうか。さらには、お互いに身分とは無関係な対等の立場で話し合い、決まったことを守り、実行するという意味で、「民主主義」的行動の先駆者でもあったのではないかと思います。
『英雄と聖人』
次が『英雄と聖人』です。これは、東大文学部の古川哲史教授が「日本倫理思想史全三巻」の最後の一巻( 一九五八年に出版) として書いたものです。と言うとなにやら堅苦しい内容かと思いきや、意外に面白いことが書いてあります。英雄や聖人は人々にとって善かれ悪しかれ模範の役を果たし、倫理・道徳的に影響を与えるので、その研究は重要な意義を持っているのでしょう。
まず「英雄」ですが、皆さんは「英雄」というと、特に日本に限った場合、誰を思い浮かべますか? もちろん、政治、経済、社会、文化、スポーツなどいろいろな分野があるので、「イチロー」など様々な顔が思い浮かぶかもしれませんが、歴史上の人物に限った場合、誰が英雄として浮かんでくるでしょう? 古川教授によれば、この本を書いた当時までの日本人であれば、「まず源義経、楠木正成、上杉謙信、豊臣秀吉、西郷南州などをおもいうかべたであろう。それらにさきだって平清盛や源頼朝、足利尊氏、武田信玄、徳川家康… … などを挙げるひとは、… … ほとんどいなかったろうとおもわれる。」中でも源義経の人気が際立って高いというのです。これに対して、平清盛、源頼朝、足利尊氏、武田信玄、徳川家康などは、英雄かもしれないが、しかしいわば「第二級」の英雄としてしか遇せられていない、というのです。
そこで前者のグループの人物の共通点を調べれば、日本民衆にとっての第一級英雄の資格がわかるでしょう。古川教授によれば、彼らに目立って共通しているのは「天寿を全うしないで比較的に早く世を去り、しかもそのさいごは不遇の境涯において迎えられた点」だとしています。
すなわち、義経は兄頼朝の追求を受けつつ諸国を流浪した果て年三十一にして衣川の館に自殺し、正成は建武の中興に大功があったにもかかわらず酬いられるところはきわめて薄く、しかも足利尊氏の大軍が京師に入るのを寡兵をもって湊川に迎えうって年四十三にして戦死し、謙信は好敵信玄との決戦が成就しないうちに雄図空しく年四十九にして越後国春山城に病没し、南州は征韓の議
が容れられずして退官帰郷し、郷党の子弟に擁せられて兵をあげたが敗れて年五十一にして城山に自殺した。
例外は秀吉で、彼は頂点まで登りつめ、六十三歳で病没しました。が、彼がその最後を迎えたのは、生涯をかけた朝鮮征伐が予定どおり進まない焦慮の最中であり、しかも自分が亡きあとの豊臣家の運命は彼の慧眼には手にとるように見えていたということで、病床で真っ暗な未来をはっきり予期しつつ六十三年の生涯を終えたのです。
ということで、「以上の英雄はみな、その程度に多少の差はあれ、悲劇裡にその生涯を終ったと見られる。そうしてこの“ 悲劇的終焉” ということが、何よりも日本民衆にとっての第一級英雄の資格であったように思われるのである。」(文中の“ ”の箇所は、原文では傍点。以下、同)と古川教授は述べています。
これに対して第二級の英雄、清盛、頼朝、尊氏、信玄、家康はそれぞれ頂点に登りつめ、あるいは登りつめる寸前で、六十四、五十三、五十四、五十三、七十五歳で没しており、「位人臣をきわめ、天寿をも比較的に全うし」たと思われます。今から思うと、家康以外はあまり長寿ではありませんでしたが、当時の人々の平均寿命から見れば、天寿を全うしたことになるのでしょう。
そしてこの「天寿における不全、事業における未完」のゆえに第一級英雄たりえたという推測を何よりもよく保証するものとして、古川教授は『平家物語』以降の義経に関する英雄伝説の展開を詳しく辿っています。そしてこの考察が本書の相当部分を占めており、義経伝説への古川教授の関心の深さがわかります。ここではもちろんそれを詳しくご紹介できませんが、義経像がどう変遷したか、そのポイントだけお伝えします。
『平家物語』では、義経は「恥を知り、情も決断もある軍将、いわゆる花も実もある英雄」として描き出そうと意図され、したがって彼の哀れな末路には触れられていません。ところが室町時代の作とされる『義経記』になると、むしろ彼の惨めな最後が詳しく語られ、哀れな末路に読者の同情を寄せるよう意図されている、というのです。そして『義経記』では、義経はおおむね「あわれな男」、すなわち「情にもろい、優美な男性」として描かれている。それも度を越していて、楊貴妃と間違えられるほどの美男子ということになっている。もはや武士らしさなどとうてい期待できず、完全に女性的・浪漫的・王朝的人物として描かれているのです。そしてこの多情多恨、優柔不断が、結局は彼を破滅へ導いたように描かれている、というのです。
ところが、元禄十三年(1700年) に刊行された『風流御前義経記』( 西沢与志作) になるとどうか? なんと彼は徹底したいわば「好色漢」に転化させられ、今や諸国好色修行をするほどの遊び人にまで成り下がっている、というのです! こうして彼は、後になればなるほど「ひよわく、可憐なものになって」いったのです。古川教授はこのことを、謡曲や「幸若舞」の「判官物」を詳しく辿って説明しています。これらにざっと目を通していると、『日本倫理思想史』第三巻という堅苦しい本の内容とはとても思えません。
いずれにせよ、物語や伝説における義経が「ひよわく、可憐になって」いくにつれて、民衆の彼に対する愛好熱すなわちいわゆる「判官びいき」がますます高まっていったというのです。こうして、民衆の英雄義経像は「ほとんどつかまえどころにないようなもの」になっていたのです。こうして義経に関する文献を辿った後、古川教授は次のような興味深い結論に達しています。
右のように観察してまちがいないなら、そのような英雄伝説の展開過程において、わたくしは日本的英雄の一特質を見いだしうるようにおもう。それが、さきに述べた、第一級英雄は天寿における不全、事業における未完のゆえに“それ”たり得たという推測である。ところで、この推測にして正しければ、われわれは“可能的”英雄をさき頃まで巣鴨に有していたということになるかも知れない。太平洋戦争の立役者たる東条前大将(1884〜1948年)は、ついに断頭台の露と消えた(もちろん、実際は「絞首刑」――大野)。彼の天寿における不全は、もはや疑いなき事実に属する。しかも彼は大東亜共栄圏建設の雄図空しく敗将となった。彼の事業における未完も、これまた明白な事実である。とすれば、彼が第一級英雄たる条件は、ほとんど整えられているといってよい。
さらに古川教授は、東条の行動を秀吉のそれと関連づけ、類似点があると指摘しています。いずれも「国力を傾けて祖国を亡国の瀬戸際まで追いこんだ点で同罪」ということです。秀吉の朝鮮征伐の実態はよく知られているので繰り返しませんが、それがいかに残忍だったかは知っておく必要があるでしょう。なぜなら、当時の兵隊たちはちょうど第二次大戦での日本軍の残虐行為の先触れとなったからです。これについて古川教授は、貝原益軒が翻刻出版した朝鮮の書物『懲瑟録』に付けた序文の一節を引用して次のように述べています。
伝によると兵を用ゆるには義(ぎ)兵、応(おう)兵、貪(どん)兵、驕(きょう)兵、忿(ふん)兵の五つがあるといわれる、そのうち義平と応兵とは君子の用いるところであるが、秀吉の朝鮮征伐は五つのどれに該当するかというに、貪兵と驕兵と忿兵とを兼ねあわせたものである、むべなるかな敗績を取ってついに大失敗を招いた、天道悪を憎むとはすなわちこの事である、と手厳しく秀吉を責めている。
ちなみに、これら五通りの兵士について、インターネットで調べたら次のような記述がありましたので、紹介させていただきます。
史書『漢書』「魏相丙吉傳」(巻七十四、第四十四)に収められているのは、古代中国・前漢の「中興の祖」と称えられる第七代宣帝に仕えた魏相と丙吉という二人の丞相の事績であるけれども、書中には次のような記述がある。「相、上書して曰く。『臣、之を聞く。乱を救い暴を誅する、之を義兵と謂う。兵が義なる者は王たり。敵が己を加し已むを得ずして起つ者、之を応兵と謂う。兵が応ずる者は勝つ。小故を恨んで争い、憤怒して忍ばざる者、之を忿兵と謂う。兵が忿る者は敗れる。人の土地、貨宝を利する者、之を貪兵と謂う。兵が貪る者は破れる。国家の大なるを恃み、民人の衆きを矜り、敵に威を見さんと欲する者、之を驕兵と謂う。兵が驕する者は滅ぶ。此五者、但人事のみに非ず、乃ち天道なり』」。
また、古川教授は津軽藩の碩学乳井貢(にゅういみつぎ)(1712〜1792) の手厳しい朝鮮征伐批判書を引用していますので、その一部の大意を紹介しておきます。
たった一人を殺すだけでも天下の一大事とすべきだというのに、罪もない異国の幾千万もの民を殺し、土地を奪って、わが富とするなど、極悪非道の極みではないだろうか。また、国内でもし誰かが民家に押し入って妻子家僕を脅し、財宝を強奪すれば、武家はこれを強盗と見なし、強奪者を征伐し、その罪を罰するのではないだろうか。太閤は異国に押し入り、人の妻子家僕を暴殺し、家国を乱奪して我が物として所有しようとしている、あるいはそれを許している。これはまさに盗賊の所業ではないか。大臣武将を異国に送り、盗賊行為を犯させ、吾が神国を盗賊国にしようするとは、なんと恥ずべきことだろう。
そのため浅野弾正長政は秀吉を諌め、まるで「狐が付いているみたいですよ」と直言した。どんな思いでこのようなことをしたかわかりませんが、正当な理由もなく異国を征伐し、日本の半分余りの人命を尽し、かつ良将明将ことごとく日本を出て異国で相互殺戮に携わらされている。こうした状態が続けば、隙に乗じて乱賊が出てくることは間違いない。そうなったら国の守りがおぼつかなくなる。だからこの征伐をおやめなさいと諌めた。すると太閤は大いに怒り、刀を抜いて長政を斬ろうとした。そこで利家氏郷が太閤を抱き止めて、長政を強制退去させた。太閤はなんと狭量であることか。とても大道を容れることのできる器ではない。
そのため浅野弾正長政は秀吉を諌め、まるで「狐が付いているみたいですよ」と直言した。どんな思いでこのようなことをしたかわかりませんが、正当な理由もなく異国を征伐し、日本の半分余りの人命を尽し、かつ良将明将ことごとく日本を出て異国で相互殺戮に携わらされている。こうした状態が続けば、隙に乗じて乱賊が出てくることは間違いない。そうなったら国の守りがおぼつかなくなる。だからこの征伐をおやめなさいと諌めた。すると太閤は大いに怒り、刀を抜いて長政を斬ろうとした。そこで利家氏郷が太閤を抱き止めて、長政を強制退去させた。太閤はなんと狭量であることか。とても大道を容れることのできる器ではない。
ところが、古川教授によれば、貝原益軒や乳井貢のこうした非難にもかかわらず、「日本の民衆は秀吉を稀代の英雄として尊敬し、そうしてこの“ 偉い奴” を記念する酔舞の行列は今なお京都・大阪の街路を練り歩いて行く。とすれば、いよいよ日本の民衆に将来東条が英雄として登場する公算が大きくなるわけである」と述べています。戦後65 年経った今も靖国神社の永久戦犯の扱い方が議論されている背景には、意識的・無意識的に東条を英雄視する日本人が相当にいると推察され、これらの人々の内面にきわめて無気味なエネルギーがマグマのように蓄積し続けているのがわかります。古川教授もそれを危惧し、結論的に次のように述べています。
天寿における不全、事業における未完が第一級英雄の条件となるごとき心性の、あまり健全とはおもわれないことだけは、これを断言して差し支えないであろう。それに、英雄がわれわれの理想的人格の類型としてどれだけ願わしいものであるかも、問題である。中江藤樹などによれば、英雄は聖人・賢人・英雄・奸雄という四段階において僅かに第三段に位置付けられるにすぎない。とすれば、英雄を最高類型とするごとき民度は低いと看做さざるを得ない。ところで日本倫理思想史上に出没した理想的人格の類型は、ひとり英雄のみに限られたわけではない。
ちなみに、上の文中にある「民度」ですが、これは大辞 林によれば「ある地域に住む人々の、生活水準や文化水準 の程度」です。が、これは社会学者や評論家などがきちん とした規準に則ってではなしに、勝手な意味合いを込めて 11 使っている場合が多いのではないかと思います。この言葉 を使う人には、また、優越感、自分は「大衆」あるいは「民 衆」ではない、ものがよく見えるインテリ・知識人だといっ たような自惚れも感じられます。もっとも無難なのは、「健 全な常識」あるいは識別力を働かせて、どの程度人物や物 事良し悪しを的確に判別できるか、その度合をさすと見な すことではないかと思います。そうすると、異国に多くの 貪兵、驕兵、忿兵を送り込むような大将を英雄視するとい うような人民は、やはり民度が低いと言わざるをえないの ではないかと思います。たとえ秀吉が部下たちの軍功に報 いるためにやむをえず他国の領土を奪おうとしたのだとし ても、やはり国際的に見てとうてい許しがたい暴挙であっ たことは事実でしょう。ですから、秀吉を諌めた浅野弾正 長政のような正気あるいはまっとうな人がいてくれたとい うのは、せめてもの慰めだと思います。
ところで、道徳を研究課題にするということは、道徳の「理想と事実の不一致」にもまたいやおうなしに直面することでもあるでしょう。古川教授は、戦時中のそうした事例を紹介しています。それは昭和19年の末か20年の初めごろのことで、教授はアメリカ空軍から東京の空を守るために松戸に駐屯していた戦闘機部隊から相談を持ちかけられたので、出かけて行き、そこで次のような話を聞いたそうです。
日本の飛行機が飛び立ってB29 を追いかけても全然追いつけない。そこで仕方がないので登載物をできるだけ降ろして、なるべく機体を軽くしようとし、とうとう機関砲とか機関銃などの武器も全部降ろしたら、ようやくB 2 9に追いつけることがわかった。が、そうなると、B29を落とすためには、いわゆる体当りをやる他に方法はない。ということで、昭和20年の初めごろから体当り戦法がだんだん実行され始めた。
が、この体当り戦法は、実際にはなかなか難しいことであって、それについては物心両面にわたる複雑な問題がある。そのような問題について調べてもらいたいというのが松戸の戦闘機部隊の指令部の要請だったのです。
また、こうした肉弾戦法が使われていた一方で、陸軍の航空部隊の中で次のような話を古川教授は耳にしたそうです。台湾の戦局が切迫してきて、もはや守りきることはほぼ不可能という見込みになり、そして日本に帰って来る飛行機もいよいよ最後の便になるかもしれないという事態になっていた。そしてその最後になるかもしれない飛行機に何人かの見習士官が乗って出発を待っていた。ところが出発前になって突然彼らは飛行機から降ろされ、その代りに俵が積まれた。実はその中には砂糖が入っていた。その砂糖をどうするのかというと、日本内地まで運び、自分の仲間、つまり航空部隊のごく限られた者だけで分けて取ろうという算段であった。しかもあろうことに、そのような卑しい話をある飛行将校が得々としていたというのです。
一方には、自分の一身を投げ出して敵機にぶつかろうとしている人々がいるのに、他方にはすでに乗っている見習士官を降ろしてまでも砂糖を積み、後でごくわずかの仲間と甘い味にありつこうとしている軍人がいたわけです。
戦時中、毛皮その他用に多くの人がペットまで強制的に供出させれらていたというのに、ワインを飲み、ビフテキを食べている人がいたようですが、現実というのはしばしば不愉快なものだと思います。
古川教授はまた「日本の聖人」について述べていますが、これについては別の機会に紹介させていただきます。